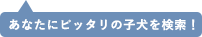ワクチンといえば、ワンちゃんが病気にかからないように接種する
注射ということはあなたもよくご存じだと思います。
でも・・・次のような疑問を感じたことはないですか?
「どうして打たなければならないの?」
「いつごろに打てばいいの?また、何回打ったら良いの?」
「必ず必要なことなの?」
「伝染病はどんな時に発生するの?」
「どんな種類があるの?」
「毎年打たなければいけないの?」
これらの疑問について、ブリーダーズがお答えしましょう!
ワクチンについて深く理解をすることは、
これからあなたの家族となるワンちゃんを守ることにもつながります。
色々な本を読んでみても、ブリーダーやペットショップの店員に聞いてみても、
そして獣医に聞いてみても、見事にバラバラな答えが返ってくるのがこの質問です。
でもこれ、誰が間違っているとか、誰が正しいとか、そういった問題ではなく、
実はある意味みな正しいともいえるのです。
それはなぜか・・・ブリーダーズがわかりやすく簡単にご説明しましょう!
生まれたばかりの子猫は、免疫系統が未発達なので、自分で免疫抗体を作ることができません。
抗体を自分で作れるようになるまでは、お母さんの母乳に含まれる移行抗体という免疫抗体により、
さまざまな病気から守られることになります。
(母猫が、ワクチンを打っていなく抗体がないと、移行抗体も当然存在しないので注意です。)
たまに母乳を飲む力のないくらい弱い子が生まれることがありますが、
その場合は、子猫に免疫力がつかなく、死に至ることが多いのもこのためです・・・
この移行抗体は、生後3週間~4週間ほどしますと母乳から離乳食に変わることもあり、
生後6週目あたりから徐々に減少し始め、12~14週目には完全に消滅してしまうのです。
この時期になると、子猫も自分自身で免疫抗体を作れるようになってきます。
しかし、移行抗体も徐々に減少するために、感染病に対する耐性が低くなってしまいます。
そこで、必要になってくるのが、感染病に対する免疫抗体の作成を補助するワクチン接種です。
(ワクチンを接種することにより、子猫が自分自身で感染病に対する抗体を作るということです。)
しかし、ここで悩ましい問題が一つあります。
移行抗体がまだ大量に残っている内は、ワクチンを打ってもバウンドし抗体を作ることができません。
つまり、子猫を守るためのお母さんの移行抗体がワクチンを拒否してしまうということです。
『母猫より受け継いだ移行抗体は、いつ切れるかは正確には分からない。
また、移行抗体が少なくなると感染症に対して無防備になる。
かといって、ワクチンを接種しても移行抗体に阻まれ、効果がないこともある。
それでも、この時期、感染病に対して何らかの対策はしておかなければならない・・・』
この問題を解決するために、考えられたのが
ワクチンプログラムです。
つまり、移行抗体が減少し始める8週目くらいから完全に無くなってしまう14週目までの間に、
日数をあけつつ、2回に渡ってワクチンを接種するという手法です。
ワクチンが効いているかどうかは、血液検査をし高いお金と時間を掛ければ調査可能です。
しかし、そんなことをするよりもワクチンを複数回打ってしまったほうが早く安く済むわけです。
検査結果を待つ間に感染病が発症してしまったら意味がありませんからね。
移行抗体が消えるタイミングは、個体差がありバラバラです。
したがって、上記の「いつワクチンを何回接種すればいいのか?」に対する回答は、
最終的に感染病に対する抗体ができればいいわけですから、どれも正しいということになります。
最近のワクチンは、技術の進歩により、母親の移行抗体の影響を受けにくくなってきています。
生後60日前後に最初のワクチンを打っている限りは、それほど心配の必要はないでしょう。
重要なのは、引き渡し前にブリーダー段階で必ず1回目のワクチンを接種していることです。
ここさえきちんと守っていれば、大切な子猫が感染症で死ぬということはまずないです!
※ワクチン接種後は、最低でも3日間は安静にさせて、それから引き取るようにしてください。
人間の予防接種の場合は、一度接種するとたいていは一生にわたり効果をあらわしますが、
猫の場合は、その免疫力は徐々に落ちてきます。
初年度のワクチン接種プログラムにより得られた免疫抗体は、約1年間効果が持続しますので
その後は、1年に1回ワクチンを接種するのが理想と言われています。
1年に1回ワクチンを追加接種することにより、下がってきた抗体価を再び上昇させ、
感染に対する免疫力を高めることができます。これを
ブースター効果と言います。
答えは、ワクチンを打たないと必ず感染病にかかるというものではないが、
その確率は、打たないときと比べて言葉で言いあらわせないくらい高くなるということです。
逆にワクチンを打ったからと言って、100%感染症を防げるということでもないです。
ワクチン自体は本来、感染病に対する予防的な性格のもので、接種していなくても、
感染源であるウィルスと接触しない限りは、発症することはありません。
しかし、ウィルスは目に見えませんので、どこで拾ってしまうかは誰にも予測ができません・・・
動物病院やペットショップなどの動物の多いところは当然として、
野良猫などが集まりやすい場所や猫カフェ、あらゆる所にウィルスは存在しています。
家の中に、滅菌状態で閉じ込めておけば、ワクチンを接種する必要はないのでしょうが、
そんな状態って、通常はあり得ないですよね?
パルボなどは、感染すると簡単に死に至る本当に恐ろしい病気です。
この怖い病気を数回ワクチンを接種することにより、ほぼ完全に防げるのでしたら、
ワクチン接種の意味は非常に大きいと言えるのではないでしょうか?
子猫の命を守るためにも、ワクチン接種は、必ず行うようにしてくださいね。
特に、子猫の引き渡しの時が一番注意を要します。
急な環境の変化でストレスを感じ、免疫力が低下して感染する確率が飛躍的に高まります。
たまに、母親の抗体がまだ残っているから、ワクチンを打たないで引き渡しても問題ないという
ブリーダーやペットショップがいますが、これは言語道断だと言わざるを得ません。
必ず、第1回目のワクチンを接種後、生後50~60日以降に引き渡しを行うようにしてください。
1.ワクチンには「生ワクチン」と「不活化ワクチン」 の2種類があります。
「生ワクチン」とは、読んで字のごとく、生きているウィルスを使用しているワクチンです。
弱毒株と言われる弱いウィルスで、ワクチン接種時に体内に入ると増殖を開始し、
非常に軽微ですが病気に感染したのと同じ状態になります。
この過程で抗体ができますので、非常に強力な免疫力がつき、持続性があることが長所です。
逆に短所としては、生きたウィルスを使っているため、体調が悪い時など免疫力が弱っていると、
本当にその病気を発症してしまう可能性があるということです。
「不活化ワクチン」の方は、死滅したウイルスを材料にしているので接種後の増殖はありません。
このため、生ワクチンに比べると免疫力が弱く、持続力も劣ります。
しかし、逆に長所としてその病原体による症状があらわれることはほとんどないです。
2.混合ワクチンの種類は、対象ウィルスの数により種別されています。
◎猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペスウイルスⅠ型で風邪の一種:猫風邪)
◎猫カリシウイルス感染症
◎猫伝染性腸炎(猫汎白血球減少症):パルボウイルスによる感染
◎猫クラミジア感染症
◎猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
◎猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)(猫エイズ)
3.混合の種類は多ければ多いほど良いという訳ではありません。
いわば、『毒』を注入するのですから、それなりのリスクがあることは理解しなければなりません。
何種混合が良いのかは、信頼できる獣医師によく相談した上で、決めると良いでしょう。
特に第1回目のワクチン接種においては子猫の成長もまだまだこれからの状態であり、
体の小さな子猫に8種以上のワクチンを接種することは危険な可能性もあります。
子猫の健康状態や、体重なども影響しますので、獣医の判断に従うのが一番でしょう。
1.感染症とは?
病原体となる微生物が、動物の体の中に入り込み増殖していくことを『感染』と言います。
感染したことによって、体の働きや仕組みにいろいろな障害が起こることを『発症』と言います。
こうした病原体となる微生物によって引き起こされる病気を『伝染病』といいます。
(他の動物や人にうつらないものは『伝染病』とはいいません。)
感染症の病原体となる細菌やウィルスなどは、非常に微少サイズのため、
肉眼では見ることはできず、光学顕微鏡や電子顕微鏡にて観察することができます。
2.感染経路は主に3つ
【空気感染】
セキやくしゃみなどで、空気中にばらまかれたウィルスや細菌を吸い込むことにより感染します。
【母子感染】
子ネコが母ネコのお腹に入っている時に胎盤を通じて感染するものや、
生まれてくる時に産道で感染するもの、母乳を飲むことによって感染するものなどがあります。
【経口感染】
ウィルスや細菌のついてる物をなめたり、食べたりすることにより感染します。
3.感染症の種類および解説
◎猫ウイルス性鼻気管炎(ヘルペスウイルスⅠ型で風邪の一種:猫風邪)
「咳」「目ヤニ」「くしゃみ」「鼻水」「発熱」「食欲不振」などの
風邪のような症状があります。
また、上記の症状の他に、下痢の胃腸症状も引き起こすことがあり、
急激に衰弱することもあります。
生後6ヶ月未満の場合は、急激な症状の悪化により
命を落とす危険性もあると言われています。
◎猫カリシウイルス感染症
猫カリシウイルスによる感染症で、高熱やくしゃみ、
鼻水、よだれ、食欲不振などの症状が出ます。
症状が長引いた場合、口の中や舌に潰瘍ができたり、
口内炎が出来ることもあります。
潰瘍や口内炎により二次感染して肺炎を引き起こした場合、
最悪、死に至るケースもあります。
◎猫伝染性腸炎(猫汎白血球減少症):パルボウイルスによる感染
子猫が感染した場合、数日の潜伏期間を経て、
食欲不振、高熱、激しい嘔吐と下痢の症状が出て、
脱水症状を引き起こします。
手当が遅れた場合、白血球が減少するため
細菌の二次感染による敗血症を引き起こし、
命を落とす恐れもあります。
成猫が感染した場合は、ほとんど無症状のため、
感染したことに気づかないことがほとんどです。
◎猫クラミジア感染症
猫クラミジア感染症は、感染してから3~10日後、
片方の眼の炎症から始まることがほとんどです。
粘り気のある目ヤニを伴う結膜炎が特徴で、
ウイルス性の結膜炎より症状が長引き、
慢性化しやすいと言われています。
感染しやすい月齢は約2~6ヶ月齢の子猫に多いですが、
人畜共通感染症の一つでもあり
猫から人へと感染したという事例も、ごく稀にあるようです。
◎猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
猫白血病ウイルスはレトロウイルス科に属するウイルスです。
感染している猫の唾液や涙、血液などを介して感染することがほとんどですが
特にケンカなどでの咬み傷から感染する確率は高く、子猫の場合は発症後の
死亡率も高くなります。
症状は、くしゃみ、鼻水、食欲不振、発熱、下痢、口内炎など有り、
その他に、リンパ性白血病や溶血性貧血、血小板・白血球減少症、腎臓病を
引き起こすことがあります。
◎猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)(猫エイズ)
人間のエイズに似ているという点から「猫エイズ」とも呼ばれていますが
人に移ることはありません。
感染経路は、猫免疫不全ウイルスに感染している猫の唾液に
多く含まれていることから、ケンカなどをした時の刺咬からか、
母体の胎盤から感染することもあります。
このウイルスは、急性期・無症状キャリア期・エイズ発症期と
感染してからの症状の出方が異なります。
・急性期
感染をしてから、約2週間以降1ヶ月程度で風邪のような症状
下痢、リンパ節の腫れがみられます。
この症状がその後1年間続く場合もあります。
・無症状キャリア期
急性期で現れていた症状が一旦落ち着き、
ウイルスがリンパ球に隠れてしまいます。
そのため、体調が良くなって病気が治ったと
勘違いされてしまうことも多いのですが
約4~5年ほどをかけて、リンパ球を破壊し、
どんどんと体を蝕んでいきます。
長い子では、この無症状キャリア期が10年ほど続くという場合もあるようです。
・エイズ発症期
無症状キャリア期を終え、エイズを発症すると、
最も多い症状が歯肉炎や歯周組織などの炎症、
口内炎、口の中の潰瘍、など、口腔内の疾患です。
その他、嘔吐、下痢、風邪を頻繁にひく、風邪が長引く、
ダニ・真菌などによる皮膚炎、体重の減少、食欲不振、脱水、などがみられます。
さらに、肺炎、胸膜炎、悪性腫瘍などがみられ、
さまざまな臓器障害を引き起すようになっていきます。
 ワクチンについて疑問を感じたことはないですか?【 ロシアンブルー・ブリーダーズ 】
ワクチンについて疑問を感じたことはないですか?【 ロシアンブルー・ブリーダーズ 】 ワクチンについて疑問を感じたことはないですか?【 ロシアンブルー・ブリーダーズ 】
ワクチンについて疑問を感じたことはないですか?【 ロシアンブルー・ブリーダーズ 】 ワクチンといえば、ワンちゃんが病気にかからないように接種する
ワクチンといえば、ワンちゃんが病気にかからないように接種する